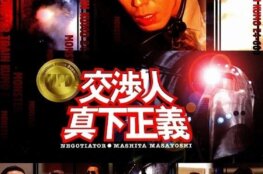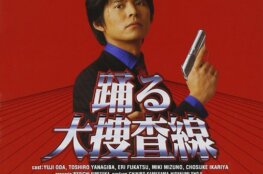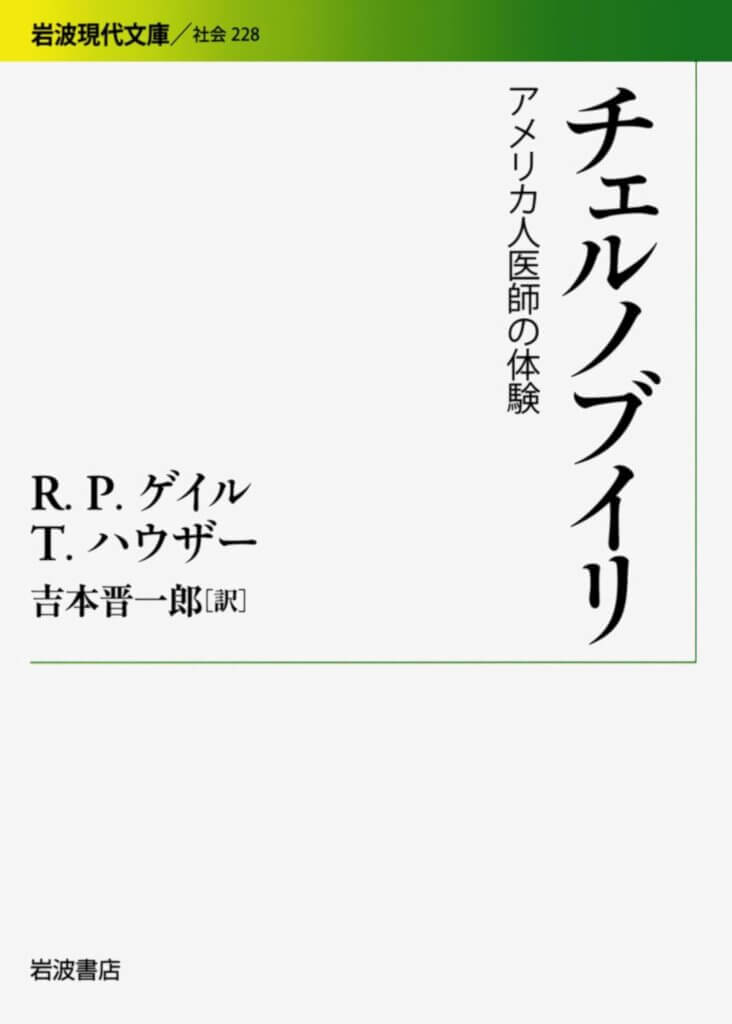
発行:岩波書店 岩波現代文庫 翻訳:吉本晋一郎 定価:1360円=税別
第1刷:2011年8月18日 原著発行:1988年
1986年、チェルノブイリ原発事故の直後にソ連に入国、被曝した人々を救うため、モスクワで医療活動に従事したアメリカ人医師の回顧録である。
日本では1988年、岩波新書で上下2巻に分けて出版されていたところ、2011年の福島原発事故を受け、改めて岩波現代文庫1巻として再刊された。
著者のロバート・ピーター・ゲイルは元カリフォルニア大学医学部教授で、白血病と骨髄移植の世界的権威として大変有名な人物だそうだ。
日本での文庫版発刊にあたって、「チェルノブイリからフクシマへ」と題した序文を寄せている。
著者は当時、医師としての使命感に突き動かされてソ連に渡ろうと決心。
ところが、まだ東西冷戦時代の末期とあってなかなか入国がかなわず、米ソ両国間のフィクサー的存在として知られていた大富豪アーマンド・ハマーの力を借りることになる。
このあたり、あえて不謹慎な感想を書けば、ジャーナリストによる国際社会の内幕を読んでいるかのような面白さ。
身の毛のよだつような被曝や治療の実情に加え、常にKGBに監視されていた滞在生活やロシア人医師たちとの葛藤や衝突なども臨場感たっぷりに描写されている。
著書はやがて、医療活動を通して対立する国家間の内情に足を踏み入れざるを得なくなる。
そして、国際社会における核開発とは何かという問題にも真正面から向き合うことになった。
中盤では当時のゴルバチョフ書記長や米国のシュルツ国務長官も登場。
あのチェルノブイリ原発事故が米ソ両国にどれだけ衝撃を与え、対応に追われた両国首脳がいかに動揺していたか、改めてよく理解できた。
共著者のトマス・ハウザーは傑作ノンフィクション『モハメド・アリ その生と時代』を著した作家。
実は弁護士も兼業していたということは本書を読んで初めて知った。
37年も前の作品なのに、終章に書かれた「核の時代をどう生きるか」という小論はいまでも十分な説得力を持っている。
日本人として、原爆、原発、フクシマとどう向き合うかを考えるのには格好の1冊と言えよう。
あえて難点を挙げるとすれば訳文で、古めかしい表現、重複した言葉が多く、いささか読みにくい部分が少なくない。
21世紀の若い人たちにも読んでもらえるよう、可能なら新訳版を望みます。
旧サイト:2012年11月6日(火)付Pick-up記事に加筆、修正
😁😭😳🤔🤓
面白かった😁 感動した😭 泣けた😢 笑った🤣 驚いた😳 癒された😌 怖かった😱 考えさせられた🤔 腹が立った😠 ほっこりした☺️ しんどかった😖 勉強になった🤓 ガッカリした😞