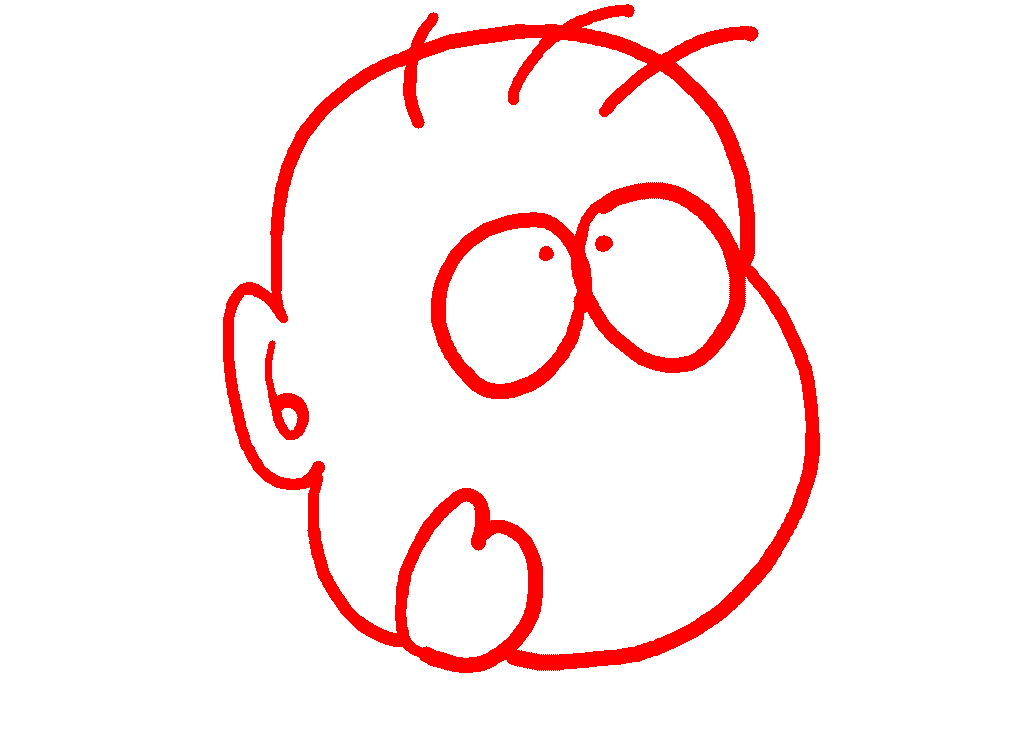上野の東京都美術館で開催中の『ムンク展/共鳴する魂の叫び』に足を運んできました(画像)。
上野動物園へパンダを見に行ったことはあるけど、その隣にあるこの美術館を訪ねたのは初めて。
と同時に、ムンクの絵画、代表作『叫び』の実物を見たのも人生で初めて。
『叫び』はPCやスマホで「ムンク」や「叫び」と打つと、オリジナルをカリカチュアライズしたアイコンに変換されるほど世界共通の記号と化しているが、本物を見たことのある日本人はそれほど多くないだろう。
この作品、ふだんはムンクの母国ノルウェーの首都オスロのムンク美術館に展示されていて、来日したのは今回の展覧会が初めてだそうだから。
ちなみに、実は『叫び』は1枚ではなく4枚あり、ムンク自身が世界に流通させるため、リトグラフで描いたヴァージョンがあることも初めて知った。
ムンクが初めて『叫び』を描いたのは30歳だった1893年。
1枚目はクレヨン、2枚目はクレヨンとテンペラ(卵黄で顔料を練って作った絵の具)が使われており、どちらもオスロ国立美術館に寄贈された。
3枚目は32歳になった1895年、パステルを使用したもの。
これもコレクターに売れたことから、ムンクが自分の手元に置いておくため、47歳だった1910年ごろに描いた作品が4枚目である。
今回、初来日を果たしたのはこの4枚目で、前述の3枚と比べてみると、まったく同じ構図ながら、中心で〝叫んでいる〟人物の表情や作品全体の色合いがかなり違う。
前3枚との最大の違いは、人物の目から瞳がなくなり、髑髏のように眼孔だけになっているところで、これが独特の迫力と雰囲気を生んでいる。
音声解説やガイドブックによると、ムンクが『叫び』の着想を得たのは29歳だった1892年1月のこと。
夕焼けに染まったニースの海岸を歩いているとき、「突然聞こえてきた自然の叫びに底知れない恐怖を感じ、その経験が元になった」と語っている。
つまり、「叫び」とは絵の中の人物の絶叫ではなく、どこかから聞こえてきた「自然の叫び」であり、彼が思わず耳を覆うほどの強さ、大きさ、凄まじさだった、と解釈できる。
ムンク自身らしいこの人物が叫んでいるわけではなく、彼が口を開けているのは「自然の叫び」に驚愕したことを表現している、と捉えるのが実は正しいのではないだろうか。
とはいえ、それでも、この人物の表情が「叫び」という行為をこれ以上はないほど的確に、かつ極めて印象的に表わしているのもまた確かではある。
とすると、「自然の叫び」に共鳴した「人間の心の叫び」が表現された作品と言うべきか。
ムンクはこのように、一度得たモチーフを何度も繰り返し作品化した画家で、『絶望』(1894年)、『メランコリー』(1894~96年)など、『叫び』のバリエーションと思われる作品も少なくない。
とりわけ印象的なのは1895年に描き始めた『接吻』で、第1作は全裸の男女がカーテンを開けた窓辺でキスしているクロッキー的な作品なのだが、描き続けるうちに油彩の重い色が重なり、カーテンが閉められ、男女とも着衣になり、キスを超えてふたりの顔が一体化してしまう。
ムンクは写真にも造詣が深く、自撮りをしてはその写真を元に自画像を描いていた。
そうした手法によって描かれた顔がまた独特の迫力を感じさせ、恋人トゥラ・ラーセンとの間で拳銃暴発事件を起こし、神経衰弱に陥った1903年の作品『地獄の自画像』が絵もタイトルもとくにすごい。
記念のグッズや撮影スポットも充実しており、平日にもかかわらず、会場は結構混雑していた。
次はいつ来日するかわからないので、少しでもムンクや『叫び』に興味のある人には一見の価値アリ! です。